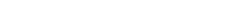ワンテンポでも遅れていたら、おそらくシュートは決まっていなかっただろう。
敵地に乗り込んだ柏レイソル戦、0-0で迎えた41分に名古屋グランパスのキャスパー・ユンカーが見せた一連のプレーは実にスムーズだった。ペナルティエリア内右側でルーズボールを拾うと、トラップしてからすかさず左足を振り抜く。ボールは美しい孤を描き、ゴール左にコントロールショットを決めた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/edef873354307d806d24dd201846c347f3b33a4c
「あの状況でシュートを打つのは、自分が今までやってきたこと」
試合後にユンカーがゴールを振り返ったとおり、一瞬の判断がポイントだった得点だろう。少しでも足の振りが遅れたらシュートブロックされるか、相手GKに防がれた可能性が高い。では、なぜユンカーはすぐにシュートを打つ決断をできたのか。
「あの状況では正直、ゴールとかキーパーの状況は見ていないです。あれは自分の直感に従ったシュートです。そこに導くうえで、自分の経験値は大きい。あの状況でシュートを打つのは、自分が今までやってきたことなので、その直感に従ってシュートを打っただけです」
ユンカーが教えてくれたのは「直感」の重要性だ。そこで必要になるのは本人が語る「経験値」であるのは間違いないが、以前の取材で脳科学者の篠原菊紀氏から聞いた「直感の“機能性”に差が生まれる要因」も、ここで紹介したい。
「最大の要因は感情です。パスが通ったなら『上手くいった』と喜び、通らなかったなら『失敗した』と悔やむ。そういう感情が良質な直感を育てます。だから喜怒哀楽を感じることはとても重要です」
ゴールを決めれば喜び、チャンスを外せば悔やむ。喜怒哀楽を表現していた柏戦でのユンカーが印象的だった。心の底からスポーツを楽しむというサッカーの大事な根本に改めて気づかされた。
🇯🇵❤️🇩🇰
これすごい。感動的。
This is crazy. So many Danish flags in the away stands ❤️ pic.twitter.com/HDUbNecCeD
— Kasper Junker (@KasperJunker) March 12, 2023