
TOKYOFMをキーステーションに放送中の「チャレンジ&カバー」で、夏の甲子園大会で優勝を果たした慶應義塾高校野球部の練習時間が短いことについて聞かれると、こんな話をしていた。
日本では量だが、欧州では質が重視される

ヨーロッパとか海外の監督は決められた時間のなかで、クオリティ・質を上げていこうっていう考え方なんだけど、日本は質じゃなくて量でそれをカバーしようとするので。
日本の労働時間が長いっていうのもそうだと思うんですけど、結果じゃなくてやった分だけで評価する。
居残り練習してることが偉いとかって、そういう風に考えられているので、それが欧州とは考え方が違うんですよね。
だから、いつも僕も日本の練習長いなぁって思いますし、Jリーグとかの話を聞いていても、それは選手がうまくなるためっていうよりかは監督がどっちかというと全部やったって思いたいから、やらせてんじゃないかなっていうようなことが多いなぁって個人的には思います。
とはいえ、逆に言うと、育成年代、こういう学生の時に何でもかんでも効率効率ってやっちゃうと効率でしか動けない人間になっちゃって、踏ん張れない大人になっちゃうんじゃないかなって僕も考えていて。
学生の時って本当に理不尽なことが沢山あったじゃないですか?なんでこんなことさせられんだとか、なんでこんなのやんなきゃいけないんだっていうのを乗り越えて、精神的に強くなるのかなぁっていうのを思ってるんです、僕は。
だから、ある程度は学生時代にそういう理不尽なことを乗り越える力を身に着けることも必要なのかもしれないなぁっていうのも思っているので、これに関しては半々。
僕が長くやったヨーロッパでは90分以上トレーニングすることはまずないですね。それは多分育成年代も一緒で。
ていうのは、90分が集中力の限界っていうのと、あとはサッカーは90分だから、90分のなかで全力を出し切ることが大事っていわれていて。
監督によっては、例えば(選手が)自主トレをしたいって言ったら、お前、俺の練習じゃ満足できないのかと、なんでお前、俺の練習のなかで自分の持っているものを全部出しきらないんだって逆に怒られるパターンもある。
日本だと真逆じゃないですか、自主トレなんでしないんだってなるじゃないですか。お前、足りないところばっかりだろ、なんでやらないんだってなるんだけど。
ヨーロッパとかだと限られた、与えられた時間で自分のベストを尽くせよと。
80(%)でやるから、余力があって、自主トレするんじゃないのって考えられるんで。
だから、僕も最初ね、それをすごい戸惑ったんですよね、日本から行く時。
いつも残ってやりたい、走りたいって言ってたら、なんでだって怒られてたんですけど。
いまはやっぱりそれを出し切ることを、限られた時間のなかで強度も質も上げてくっていうのを意識していますね。

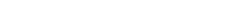





![サッカーマガジン 2024年 08月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Z94iyLEjL._SL160_.jpg)

![サッカークリニック 2024年 08月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51fnm5HxxlL._SL160_.jpg)















コメント
一方のクリロナは居残り練習しまくりで
ストイックと評されていた
タイトルでまた海外ageかよと釣られかけたけど全部読んだらいい記事だった
やっぱりマガトは日本に向いてると思う
伊良子スタイルで行け
良くも悪くも「持って居るものが全て、それで勝負する」ってマインドなんだな
単純にオーバーワークは怪我の元だから
あまり練習させたくないのだろう
コーチの管理問題にもなるしな
要は質でも量でも勝て!って事だろ?
90分全力の練習が、次第に100分120分ってこなせるようになる。
量に偏り過ぎている弊害は日本の各所にあるから、考え方を変えていく必要はあるね
学生時代は仮に学びになっても、お金を稼ぐ段階で考え方がそこのままだと組織の足を引っ張る存在になってしまうし
>>8
モーレツ社員時代の方が幸福度が高かったという悲しい現実
まあ1万時間なるモノがあるからなあ。
やらかし癖のある奴がこれ言っても説得力ないな
>>9
単純に他の国が成長したからじゃねえかなそれ 世界で重視されるのはソフトウェアとかだけど日本そこ弱いし
>>11
お前にそんなの判断する力ねーからw
>>12
ソフトウェアめちゃくちゃ弱いからな
中抜き構造すぎて技術ある癖にまともなもの作れないのもあるけど
クリスタがAI搭載しようとしたの猛反発受けてフォトショに先越されたり、なんか色々問題あるわ
相撲は1分
100メートルは10秒の練習時間で良いのか?
と一応投げかける
高校野球ですら、アメリカに投球多すぎて使い物にならなくなると言われて30年言われてるのに、サッカーも親善試合本気なのもおっさんの精神論体質は変わらん
日本は条件が一緒ではない
スポーツなら生まれつきの体較差があり
他の業種なら英語や地理的なハンデがある
つまり欧米を超える努力は必要
ま、まず解決すべきは少子化だな
>>14
ソフトウェア技術って今の日本の文化とめちゃくちゃ相性悪いんだよ
組織の秩序を優先する風土はIT技術のスピード感に付いていけないし
一人の天才が何十人ものエンジニアより多くの価値を生み出せる構造は、出る杭を嫌う文化には合わないし
年功序列で権力が増えていくシステムでは最新技術に理解の無い老人ばかりが決定権を持つことになるし
>>7
それやってると怪我して終わるよ
>>18
そんなことはないよ。
もう少し社会経験積めばわかるようになる。
一般的には量が求められてるからね
>>16
親善試合は本気出すだろ
なんの為の親善試合だよ
弱い日本にそんな余裕無いわ
ベンゲルもグランパスの選手たちが居残り練習しようとするから止めるのが大変だったと言っていた。
やりたがらない選手をトレーニングさせた事はあっても
やりたがる選手を止める経験は日本に来て初めてだったと…
ただ、上記の監督と同じように
「私のトレーニングに全てを出し切れ!」と注意したらしい。
>>9
自分の世界しか知らなければ幸福でいられるって事だな
>>20
年功序列はなんだかんだ日本人の文化に合ってて、それを外して失業率が高くなるような社会を望まないと思う。
結局、たくさんの人に仕事を無理してまで割り振ろうとするから仕事の単純化や効率化はあんまり進まないと思うぞ。
仕事を単純化することは老害が嫌がるし、人を減らすということには弱者が嫌がる。
ヨーロッパやアメリカでも練習練習また練習とその競技に全てを捧げてる様なスーパーストイックマンがいる一方で才能あるのに遅刻や夜遊びで練習せずに堕落していく奴もいる
結局何が正解かと言われたら分からないよね
個人が技術の習得や向上に必要と思えばやればいいだけ
だから吉田はロングフィード上手くならなかったのかとすら思ってしまう
>>27
合同練習だけでは個人の足りない部分は補えないからなぁ
いつの時代もトレーニングにはその時代の旬があって
今は90分がベストとされているけど
20年後にはどうなっているか分からんね
>>22
そうなるよな、ご老人は
>>29
まあ中学生には分からないだろうけどな
勉強頑張れよ
>>18
相性悪いと思うけど、どっかの分野で世界的に一目置かれてるみたいなのはあっておかしく無いと思うわ GAFAみたいに覇権握るのは無理だろうけど(これは他の国もだけどさ)
これで向こうから選手来るだけで日本から行った選手通用しなければ向うの育成が正しいんだけど
現実は逆だからな
まあやりたくない人はやらなくていいという風にすればいいだけなんだけどね
結局は結果だけだし
なお日本の大東亜戦争でアジアの植民地が独立したのは評価されない模様。
さあてどうだろうね
このような意見は斬新ではない、むしろさんざん聞かされてきたことだ
さてここで疑問を抱く じゃあ非効率な練習をやって日本のサッカーはレベルダウンしたのだろうか?
まったく逆ということはみんなよく知っての通り
岡崎が陸上のトレーナー雇ってフォーム改善しましたなんてことが報道されたことあったがどう捉えたらいいのだ?
思うに吉田の意見は古いのかもしれない
だってこのような意見は10~15年前に多く聞かれたものだから
吉田は10年以上Jでやっていないのだから今のやり方をどれだけ知っているのだろう?